- ホーム
- ブログ
ブログ
ゆらぎ世代の内臓の冷えには座浴で体の芯から温めよう
2024/10/28こんにちは!
岸田です。
気温が難しくて、服装選びに悩みます。
施術する際もエアコンをつけるべきかどうか迷います。
ご来店時の様子でつけたり消したりしている状態です。
夏は冷えを感じていなかった方も、冷えを自覚しているという方が増えてきました。
ということで、温めメニューのご要望が増えてきたなと思う今日この頃です。
体の冷えを放置すると起こること
冷えを放置すると様々な形で調子を崩してしまいます。
- 肩こり
- 寝つきが悪い・眠れない
- 頭痛
- 疲労・倦怠感
- 胃腸の不調、便秘・下痢
- 頻尿
- 風邪症状
などの不調を感じたり、悪化したりします。
また、現代人は低体温の人が多いと言われていて、エアコンなどにより体温調節の機能が低下していたり、運動不足の人が多かったり、食生活の乱れだったり、そしてストレスというのも原因だと考えられています。
低体温は病気ではないですが、体温が低いことで免疫力が下がり病気に繋がることから「冷えは万病のもと」と言われているのではないでしょうか。
温活にピッタリ!座浴効果
生活習慣やエアコンなどからくる冷えだけでなく、ゆらぎ世代は、卵巣機能の低下や女性ホルモンの減少などで自律神経が乱れやすく、お腹周りや下半身に冷えを感じます。
若いころから冷え性だった方は更年期でさらに冷えが悪化する傾向にあると言います。
生理痛や不妊といった女性特有のお悩みなどで座浴を活用される方も多いですが、内臓が冷えやすいゆらぎ世代にも断然オススメします。
座浴は、体の内側から温めてくれて、お腹周りの温まりを特に感じられます。
体が温まると血流が良くなることはもちろんですが、腸を温めることで免疫力も高めることができます。
そして、「温かい」は強張った体をリラックスさせ自律神経も整えてくれます。
当店ではテントの中に入って全身でハーブを味わってもらうことや、視界を遮ることでさらにリラックス効果もありますよ。
まとめ
スマホからも離れ、座ってボーっと自分の呼吸に意識を向けてもらうことで精神と体のリラックスができる座浴。
体の芯から温めて、美容と健康のケアに活用していただきたいオススメメニューです。
ただ単に、体を冷やさないようにだけするのではなく、体を冷やさないように心掛けながら、冷えを改善させ体温を理想的なところまで上げていくことが温活です。
体温が1℃下がると免疫力が30%低くなると言われていますので、体温を上げるためにも内臓から温めることは効果的です。
また、体が冷えていると、不眠、便秘や肌荒れ、メンタル的にも影響を受けてイライラや気分の落ち込みなどにも繋がってしまいます。
体の芯から温める習慣を取り入れて、自己免疫力を上げていきましょう!
温める飲み物で簡単お手軽温活
2024/10/24こんにちは!
岸田です。
我が家では、「そろそろココア買ってきて」とリクエストが入ると、寒くなってきたんだなと季節の変化を感じます。
夏場は冷えている実感がなかった方も、徐々に実感してくるのかもしれないですね。
夏の疲れが今になって出てきている方も多いようで、お店では座浴などの温めメニューを希望される方が増えてきました。
冷えは体からのSOS
冷えは年中起こります。
体の中を温められた血液が全身を巡ることで、体は温まりますが、加齢・冷たい食べ物飲み物の摂りすぎ・冷房で冷やしすぎた体・運動不足・ストレス、体質などでも冷えの一因となり、血液の流れが悪くなってしまうと冷えを感じます。
冷えの種類は人それぞれありますが、大きく冷えの不調でまとめると
- 肩こり
- 腰痛
- 胃腸の不調
- むくみ
- 肌荒れ
- 生理痛・生理不順
- 代謝の低下
などなど。
中でも、免疫細胞は腸で約7割集まると言われているので、お腹が冷えていると免疫力の低下に繋がります。
温める飲み物で手軽に冷え対策
冷やさない生活の第一歩として、気軽に手軽に飲み物で冷え対策していきましょう。
- 白湯
胃腸を温め消化機能を高めてくれたり、血行を良くして基礎体温を上げてくれます。
白湯は朝起きてからと就寝前に飲むのがオススメです。
- 発酵茶
紅茶・ウーロン茶・ほうじ茶・玄米茶・・・などありますが、最も温め効果が期待できるのは、紅茶とプーアール茶です。
ただし、紅茶はカフェインも多いので、摂り過ぎは逆に体温を下げてしまうのでNGです。
また、紅茶を飲む際に砂糖が欲しいという方は、温める効果のある黒砂糖やハチミツで甘みをプラスしてください。
白い砂糖は体を冷やす働きがありますよ。
- 生姜
生姜湯・生姜紅茶・ハチミツ生姜・・・などありますが、生姜は言わずと知れた温め食材。
血行を良くし、胃腸の働きを助け、消化吸収が良くなります。
- ハーブティー
ルイボス・カモミール・シナモン・ローズマリー・・・体を温めるハーブティーはいろいろあります。
ハーブごとで効果・効能があるので、自分に合うものを探してみるのもいいですね。
シングルで飲んでも、ブレンドしても楽しいおいしいですね。
- ココア
血行を促して、体を温めてくれます。
また、体が温まる時間を長く保ってくれます。
ホットで飲めばなんでもOKというわけでもなく、飲み物には体を温める作用のあるもの、冷やす作用のあるものがあります。
急須で入れた温かい緑茶っておいしいですし、冬に好んで飲んでいるというのもよく伺います。
風邪予防対策などで摂るのは良くても、冷え対策としてはカフェインが多く含まれているので向いていません。
そして、カフェインといえばコーヒーも同じくです。
コーヒーには血管を収縮させる働きもあるので、手足が冷えやすくなってしまいますので、ほどほどにしましょう。
夏の定番、麦茶は体を冷やす作用のある大麦が原料で、冷え対策とは正反対の飲み物です。
まとめ
気温が低くなってくると、体の深部を温めようとして中心に血液が集まってくるので、手足の冷えを感じやすくなってしまいます。
上着やカイロなどをうまく使いながら冷え対策ももちろん大切ですが、体の中から温める方法も取り入れていきましょう。
温めなければとガバガバ飲むのではなく、毎日の水分補給の一環として適量を飲んでくださいね。
アチアチのホットでなければいけないということはないですが、体を温める目的であれば常温以上で飲んでほしいです。
寒さが本格的になる前に体を温める習慣で免疫力を上げていきましょう!
秋は睡眠に向き合って睡眠習慣の改善とリセットしよう!
2024/10/21こんにちは!
岸田です。
寝ようとお布団に入ると少しひんやり冷たさを感じて、季節の変化を実感している今日この頃。
秋の夜長と言われるように、日照時間が短くなり日が落ちるのが早くなりました。
秋は睡眠が取りやすい時期となり、秋~冬にかけて冬眠する動物のように、人にも本能的に備わった体のリズムとして備わっていると言われています。
夏の猛暑を耐え抜き、生活習慣の乱れなどで、疲れた身体をこの睡眠が取りやすい季節にしっかり眠って回復したいものですが、秋になっても睡眠の質が改善されずしっかり眠れていない方が多いようです。
暑すぎず寒すぎず寝やすい季節なのに、眠れていない方が多い原因と解決法で睡眠の質をリセットしていきましょう!
睡眠の質が秋になっても上がらない原因
日中はまだまだ暑い日も多いですが、朝晩が涼しくなりました。
睡眠は温度や湿度によって左右されるので、今の時期は睡眠が取りやすい時期と言えるのに睡眠の質が上がらないのはどうしてなのか…
- 夏の疲れを引きずったまま
- 日照時間が短くなったことで体内時計が乱れている
- 寒暖差に対応できていない
夏場の冷房による寒暖差などによる自律神経の乱れが改善されないまま秋となり、今になって夏の疲れがにじみ出てきていることでの睡眠の質の低下。
日照時間が短くなり、睡眠を促すメラトニンが出やすくなり、感情を安定させる働きがあるセロトニンの量が減少することで、脳の活動が低下して眠くなりますが、十分眠っても疲労感や憂鬱感を感じやすくなります。
夜寝るとき暑く感じていたのに、朝方寒かったりと、暑い・寒いで目が覚めてしまったり、寝ている間にも寒暖差があり自律神経が乱れやすいです。
まだ夏の寝間着のまま、寝具のままだという方もいるかもしれません。
季節だけでなく、女性ホルモンの分泌のリズムが崩れるゆらぎ世代は、自律神経の乱れに加えて、寝汗・ホットフラッシュなどもあり、寝入りの体温調節がうまく行えずに睡眠の質が低下しやすくなります。
そして、全世代に共通なのが、秋の夜長に夜更かしをしてしまったり、ド定番となっている寝る前のスマホ。
スマホのブルーライトは睡眠の質が下がりますので、寝る1時間前にはスマホを置いておくのが最適です。
睡眠の質向上させるために
- 朝日を浴びる
朝の光を浴びてセロトニンを増やしましょう!体内時計のリセットにもなります。
- 昼寝
季節の変化で体が疲れているときは、慣れるまで無理せず昼寝を取り入れるのも有効です。
ガッツリ寝るのではなく、15時くらいまでの時間で10~15分軽く目を閉じるだけで効果があります。
- 湯舟に浸かる
肌寒くなっている体を温めることはもちろんですが、活動モードからリラックスモードへの切り替えにもなります。
寝る前の1~2時間前に熱すぎない38~40℃のお湯に20分以上、全身浴でしっかり浸かってください。
適度に体を動かして筋肉を緩めることも睡眠にとって効果がありますが、夜にハードな運動をしてしまうと体内リズムが狂ってしまうので睡眠には向いていません。
夜、特に就寝前に運動を取り入れるのであれば、ゆっくり呼吸をしながら軽いストレッチが最適です。
手足もひんやりしてくる時期なので、手首や足首をくるくるとゆっくり回して、温めるのもオススメです。
日常の動きに少し負荷をかけてみるのも運動になりますし、暑すぎず寒すぎずの気持ちいい時なので、朝少し早起きして朝の散歩などしてみるのもいいですね。
そして、就寝前のスマホタイムが癒しだという方は、ホントは1時間欲しいですが、せめて30分前には携帯を置き、腹式呼吸で深い呼吸をお布団の中で行ってみてください。
人は寝ている間に体、脳を休め回復させますが、睡眠の質が低下すると十分に休まることなく疲労回復の効果も低下してしまいます。
日常のパフォーマンス力を上げるために睡眠がなにより大切です。
まとめ
夏は夜でも猛暑で気温も湿度も高く、眠りが浅くなりがちなので、疲労回復がしづらい季節、そして冬は寒さによって睡眠が取りづらくなります。
気候的に今の時期が睡眠のとりやすい時!
夏の疲れがまだ残っている今こそ、睡眠の質を上げて体も睡眠もリセットしないとです。
そして、今の時期に夏の疲れをリセットして、冬に備えていくことが必要になります。
夏場は冷え対策をする気になれなかった方も、ぜひ冷えた体をしっかり温めて、強張った心と体をしっかり休息できるように睡眠に向き合う時期にしてみてはいかがでしょうか。
過ごしやすくなった季節の落とし穴 胃腸元気で免疫力UP
2024/10/16こんにちは!
岸田です。
最近、周りで体調を崩している方が増えてきました。
いろんな種類の病名付きの熱症状がありますが、流行りには乗りたくないです…
好きで乗るわけではないですが、自分の免疫力をあげて自分で身を守っていかないといけないですね。
免疫は腸が関係していますが、夏~秋にかけては胃腸の不調も出やすい時期です。
少し胃腸に不安がある方も、全然大丈夫な方も、免疫を上げていくために腸活・温活していきましょう♪
秋に感じる胃腸の不調と原因
「食欲の秋」と言われ、秋~冬にかけて食欲が上がる方も多いかもしれません。
気温が下がってくると、体温を維持しようと体はエネルギーをため込もうとして食欲が増すなどと言われますが、おいしいを満喫して食事ができるのは胃が元気の証拠です。
しかしながら、
- なんとなく食欲が出ない
- 食事の前後に胃が痛む
- ゲップが良く出る
- 便秘と下痢が交互に起こる
など、胃腸の不調を感じている方も少なくありません。
原因1:夏の食生活のなごり
暑すぎた夏を乗り切るために水分をたくさん摂ったり、冷たい飲み物や食べ物を口にする機会が多くなかったですか。
まだまだ日中は暑い日もあるので、そのまま夏と変わらず過ごしていないでしょうか。
冷たいものの摂り過ぎは内臓の冷えを招いて、胃腸機能を低下させてしまいます。
そして、夏のように汗が多く出ないのに、水分を多く摂りすぎていると胃液が薄くなり、胃腸機能を低下させてしまいます。
原因2:寒暖差・気圧の差
朝晩と日中の気温差が7℃以上あると寒暖差疲労を引き起こすと言われていますが、自律神経が対応できなくなり、胃酸が過剰分泌されてしまいます。
天候の変化によって気圧が一気に低くなることも原因となります。
原因3:食べ過ぎ
夏の疲れを引きずっている胃の状態なのに、過ごしやすくなり食欲が復活したことで、ついつい食べ過ぎていたり、ストレスで食べてしまう・ドカ食いしてしまうと消化が追いつかず胃が悲鳴を上げてしまいます。
胃腸の回復で免疫力UP
- 体を温める飲み物や食べ物、食材を食べる
冬が旬のものや寒い地域でとれるもの・発酵食品・ショウガ・ニンニク・香辛料など
紅茶・中国茶・ココア・ほうじ茶など
- 湯舟にゆっくりと浸かる
38~40℃のぬるめのお湯に20分ほど
全身浴または半身浴でもみぞおちが浸かる程度で
- お腹マッサージ
おへその周囲を時計回りに円を描くようにマッサージ
お腹を温めてから行ったり、温め効果のあるオイルなど使うと尚良し
腸内環境を改善することを腸活と言いますが、一番簡単で大切な腸活は、胃腸に負担がかからない消化に良いものを摂ることや胃腸への負担を軽くするためにはよく噛むことです。
乱れた自律神経を整えるために、生活習慣を見直してみましょう。
まとめ
気候は次の季節へ向かっていますが、体の中は夏の生活習慣で内臓が冷えている状態のままだったりします。
温める食材や飲み物を摂ったり、体を動かして血行を良くしたり・・・体の中からも外からも温めていきましょう!
朝、起きた時にお白湯を飲むことに抵抗が少ない季節にもなりましたし、是非挑戦してみてください。
体の冷えは、心にも体にも影響します。
体調の崩しやすい季節でもあるので、免疫力を上げるためにも温めることオススメします!
夏の疲れや寒暖差で体への負担が大きい季節!回復と予防に大切な4つの方法
2024/10/10
こんにちは!
岸田です。
以前働いていた頃のお客様と今もありがたいことにお付き合いをさせていただいているのですが、保育園がどうとかランドセルがどうとか話していたと思っていたら、先日お子様をお店に紹介してくださいました。
時の流れは早い…早すぎる…オトナになっている…
夏バテを引きずっているようで、お疲れのご様子でした。
夏バテのような症状が続くことを秋バテとも呼ばれます。
せっかくお出かけもしやすくなった季節、そして食べ物がおいしい季節なので元気がないのはもったいない!
季節の変わり目は体調を崩しやすい季節でもありますが、夏の生活習慣で弱っている体を回復させていきましょう。
秋バテ、寒暖差疲労
暑すぎた夏がいつまで続くのかとドキドキしていたら、突然秋めいて、朝晩の暑さも少し和らいで過ごしやすくなってきましたが、日中との気温の変化に体が追いついていけずに体調は不安定になったりします。
1日の寒暖差がとても大きい。日ごとによっても気温の変化が激しい。
- 体がだるい、疲れやすい
- 頭痛、頭重感
- 気分の落ち込み、イライラ
- 肩こり
- 冷え
- 胃腸の不調
- 眠気
など、体の不調を感じている方も多いかと思います。
季節の変わり目というのは体調を崩しやすい時期ですが、秋の不調は「秋バテ」や「寒暖差疲労」と言われますが、原因不明の体調不良「不定愁訴」を引き起こします。
自律神経の乱れが原因
- 夏の生活習慣の乱れ、疲労残り
夏の猛暑と汗だくでグッタリと疲れやすい季節ですが、夏の暑さを回避しようと、冷たい飲み物や食べ物を摂り過ぎていた「内臓の冷え」、冷房の中で活動していたことが多かった「冷房による冷え」
体の中は冷えていて血流を低下させて、自律神経のバランスが乱れていることで疲れやダルさなど引き起こします。
また、日中が今も暑いときもあるので、まだまだ冷たいものを摂りがちだったり、裸足にサンダルや薄着だったり、寝具もパジャマも夏のまま…などの人もおられます。
- 気温や気圧の変化
寒暖差が7℃以上になると寒暖差疲労が生じやすいと言われます。
気温の変化に対応しようとエネルギーの消費が激しくなるので、疲れやダルさが出てしまいます。
季節の変わり目不調からの回復4つの方法
- 服装
変化の大きい気温に対応できるように脱ぎ着できるもので、体温調節を心がけましょう
- 食事
温め食材を摂ることや良く噛むなどして胃腸を温めることと負担を軽くしましょう
- 入浴
全身を温めるにはお風呂が最適です
頑張る交感神経を落ち着かせてあげましょう
- 睡眠
心身の回復にはやはり睡眠が大切です
成長ホルモンが活発になる22時~2時には寝ましょう
ポイントは自律神経の乱れを整えることです。
そして、冷えは大敵。
夏場は気づいていない冷えが、今影響しています。
動きやすい季節になりましたので、運動なども取り入れながら、血流や代謝をあげていきましょう。
まとめ
一年中を通して冷えは起こります。
冷えは万病のもと。
自律神経の乱れも年中、耳にします。
そして、不定愁訴なんてずっと感じているという方も少なくない。
ですが季節の変わり目でさらに悪化させないようにしてもらえたらと思います。
わけのわからない気候で季節がめちゃくちゃですが、そのめちゃくちゃに対応しようと体は頑張ってくれています。
体が無理なく働けるように、冷やさない・休息で環境を整えていきましょう!
関連エントリー
-
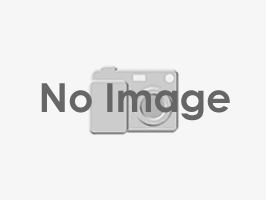 「今年こそ頑張る」がしんどくなる理由
こんにちは!岸田です。年が明けると、自然と耳に入ってくる言葉があります。「今年こそ頑張ろう」「今年は変わりたい
「今年こそ頑張る」がしんどくなる理由
こんにちは!岸田です。年が明けると、自然と耳に入ってくる言葉があります。「今年こそ頑張ろう」「今年は変わりたい
-
 やる気が出ない夜に、無理に前を向かなくていい
こんばんは。岸田です。今日も一日、おつかれさまでした。やらなきゃいけないことは、きっとまだ少し残っているけれど
やる気が出ない夜に、無理に前を向かなくていい
こんばんは。岸田です。今日も一日、おつかれさまでした。やらなきゃいけないことは、きっとまだ少し残っているけれど
-
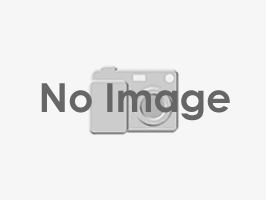 本来のリズムってどうやって戻すの?|朝・昼・夜から整える体と心の整え方
こんにちは!岸田です。帰ってきて、ごはんを作って、片づけて。「ちょっとだけ座ろう」そう思ったはずなのに、気づい
本来のリズムってどうやって戻すの?|朝・昼・夜から整える体と心の整え方
こんにちは!岸田です。帰ってきて、ごはんを作って、片づけて。「ちょっとだけ座ろう」そう思ったはずなのに、気づい
-
 お正月、もうずいぶん前のことみたい
こんばんは。岸田です。まだ1月。カレンダーを見れば、新年が始まって、まだ1ヶ月も経っていません。それなのに、お
お正月、もうずいぶん前のことみたい
こんばんは。岸田です。まだ1月。カレンダーを見れば、新年が始まって、まだ1ヶ月も経っていません。それなのに、お
-
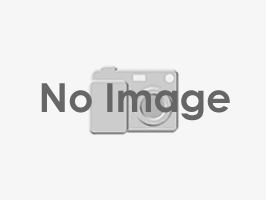 2月に体が重くなるのは、巡りが止まっているからかもしれません
こんにちは!岸田です。「最近、なんだか体が重い」「特に何かしたわけじゃないのに、だるさが抜けない」お仕事されて
2月に体が重くなるのは、巡りが止まっているからかもしれません
こんにちは!岸田です。「最近、なんだか体が重い」「特に何かしたわけじゃないのに、だるさが抜けない」お仕事されて
private salon 【nico heartily】
忙しい日々も笑顔で過ごせますように。
ご予約お待ちしております。
電話番号:072-668-7436
受付時間: 10:00~20:00(最終受付18:00)
定休日 : 不定休
所在地 : 大阪府高槻市大畑町15-1ピュア大畑1-3 サロン情報はこちら

